SONYの純正調望遠レンズ「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS」をレビュー!

念願だったSONYの超望遠レンズである「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G」を購入したのでレビューします!
「FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS」は、2019年に登場した比較的に古いレンズとなります。
新しいSONYの某連レンズとしては、2025年に登場した「FE 400-800mm F6.3-8 G OSS SEL400800G」があるが、400mmスタートということで、使い方が難しい印象があります。
サードパーティ製品にも200-600クラスの超望遠レンズがあるが、純正レンズだと以下のメリットがあります。
- SONY純正レンズであるため、テレコンが使える
- インナーズーム
デメリットとしては、サードパーティ製品と比較すると価格や解像度などで劣ることがあります。
実機で見た限り、自分の使い方ではSONYの200-600で十分だったので、こちらの製品を購入しましたので、レビューしていきます。
SEL200600Gは中古相場で約18万円
購入したSEL200600Gは、新品だと25万円ほどする高額なレンズとなります。
サードパーティ製品ですと、おおよそ12万円〜15万円ほどで購入することが出来ますので、純正レンズですと+10万円ほどします。
しかしながら、SEL200600Gは登場から6年経過しているため、中古相場でも安定してきており状態が良くても18万円ほどで購入することができるようになりました。
状態の良いものを選択することで、コストパフォーマンスを良く超望遠レンズが入手可能と判断し、今回は中古のレンズを購入しております。
インナーズームなので、埃やチリは入りにくいため、長く使えることを祈りたいです。
SEL200600Gの機能を簡単に説明
SEL200600Gの最大のメリットは、200mm~600mmの焦点距離にあります。

600mmという超望遠な距離から、200mmの望遠端までカバーできるちょうど良い距離感が好印象です。
スタートがSEL400800Gのように400mmスタートだと、被写体との距離の調整が難しいです。
しかしながら、200mmだと比較的に調整しやすいです。
特に三脚を使った撮影の場合、自分で距離を調整する手間を考えると200mmは本当にありがたいスタートラインであると感じました。
続いて、SEL200600Gのスイッチ類について見てみましょう。

それぞれの操作を表にまとめてみました。
| 名称 | 設定/内容 | 説明 |
|---|---|---|
| AF / MF 切替 | AF / MF | AFで自動フォーカス、MFで手動ピント調整。AFが迷う場面で切り替え可能。 |
| FOCUS RANGE(フォーカスリミッター) | FULL / ∞–10m | AFの探索範囲を制限し、遠距離撮影時のピント迷いを防止。 |
| OPTICAL STEADY SHOT(OSS) | ON / OFF | 手ブレ補正の有効/無効。手持ちではON、三脚撮影ではOFF推奨。 |
| MODE(手ブレ補正方式) | MODE 1 / 2 / 3 | 撮影用途に応じて補正方式を変更。流し撮りや動体追従対応。 |
よく切り替えるであるMODEについてまとめてみましょう。
MODE 1:標準補正(一般撮影向け)
MODE 1は最もバランスの良い補正モードで、静止した被写体や通常の撮影に適しています。
上下左右全方向の手ブレを補正するため、特に意図的な動きがない撮影では、このモードを使うと安定した結果が得られます。
例:風景、月、建物、止まっている動物、一般的な手持ち撮影
MODE 2:流し撮り専用(水平移動の被写体)
MODE 2は流し撮り撮影のためのモードです。
カメラを横方向に動かしながら被写体を追従させる際、横方向の補正は抑えられ、上下方向のみ補正が働きます。
意図した動きを妨げず、背景に動感のある写真を撮りやすくなります。
例:飛行機、新幹線、車、走るスポーツ競技など
MODE 3:不規則な動き向け(野鳥・スポーツ・航空機)
MODE 3は動きが予測しにくい被写体に最適化された補正モードです。
補正の介入がより動体追従に最適化され、必要な補正は強く働きつつ、追従動作は妨げません。
特に野鳥撮影ユーザーに支持されています。
例:野鳥、航空機(旋回時)、動物、スポーツ撮影
SEL200600GへROLANPROのレンズカバーを取り付け
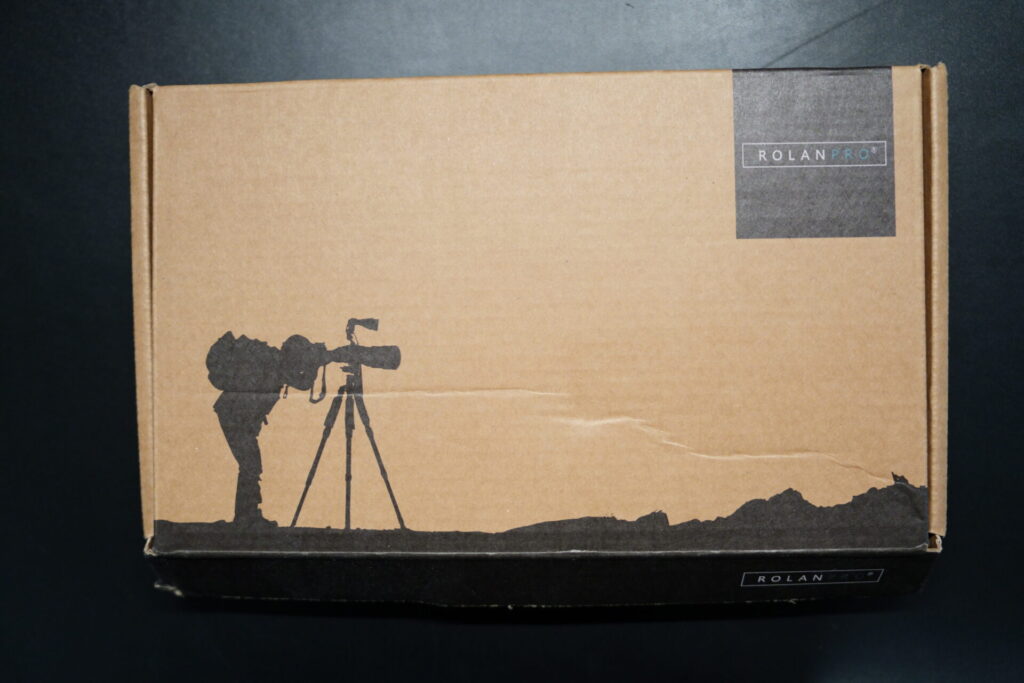
状態の良いレンズを購入したため、せっかくなのでレンズカバーを取り付けます。
今回購入したレンズカバーは、ROLANPROのグレーのデジタル防水レンズコートとなります。

名前のとおり四角形型のデジタルな迷彩柄をしたレンズコートとなります。
望遠レンズは、主に冬に使うことが多いため、雪にカモフラージュできるこちらのタイプを選択しました。

レンズへ取り付けると、ピッタリサイズであることがわかります。
特にレンズフットとレンズ側の取り付けは、かなり難しいです。
「サイズが間違っているんじゃないか?」と思うほど全く入らないので、1時間かけて少しづつはめ込んでいく作業となりました。
その他のマウント部分を含むカバーに関しては、取り付けが簡単ですが、破損しないように注意しながら取り付ける必要があります。
SEL200600Gへアルカスイスプレート対応レンズフット「Leofoto SF-02」を取り付け

SEL200600Gに同梱されているレンズフットは、アルカスイス互換ではありません。
そこで、純正のフットレンズを取り外して、Leofotoの「SF-02」へ交換します。

SEL200600Gのフットレンズは、ネジを回すことで簡単に外すことが出来ます。
SF-02の取り付けもネジで固定するだけなので、脱着は直感的に行うことができるでしょう。
「SF-02」のアルカスイスプレート以外の特徴としては、Leofotoのワンタッチストラップにも対応している点が挙げられます。

Leofotoのワンタッチストラップは「SP-01」となっております。
超望遠レンズは重量も重たいので、頑丈なストラップを別途用意する場合に、簡単に脱着できる仕様は利便性を向上させるでしょう。
SEL200600Gへすべてのアクセサリをつけた感想

防水カバーを取り付けたことで、少しばかりの防水であれば気にせずに使えそうです。
しかしながら、カメラ本体であったりマイクに関しては防水対策が出来ていないので、課題として残るでしょう。
Leofotoのフットレンズは、安定して固定されており、手で支えるには良い大きさです。
デメリットとしては、金属製であるため、冬は手袋越しでもひんやりとした冷却が手まで伝わってしまいます。
総合的には満足しており、あとはこのレンズのオーナーの腕試しと言ったところでしょうか。
α7CII用のSmallRigのハンドグリップとの相性は悪い
最後に使用しているα7CIiとの相性についてです。
以下の記事にて紹介したSmallRigのハンドグリップを装着しています。

SmallRigのハンドグリップを装着すると、レンズとグリップとの空間が狭まるデメリットがあります。
案の定、レンズカバーを装着したSEL200600Gとの相性は悪く、下の画像のように指が置くまで支えることが出来ませんでした。

SmallRigのハンドグリップを外すと、下の画像のように指を置くまで支えることが出来ます。

しかしながら、レンズカバーを装着したことで、どちらにしても中指がレンズと接触してしまいます。
「どうせ中指が接触するなら」「支えるのはカメラではなく、レンズ側」と考えた結果、SmallRigのハンドグリップを外すことはありませんでしたが、デメリットであることは間違いないでしょう。
α7cIIは、コンパクトな設計であるため、200-600クラスのレンズを使用することは、あまり想定されていないように感じます。
SEL200600Gのサンプル撮影して作例をご紹介!
SEL200600Gで野鳥を撮影してみたので、サンプルとして載せます。
撮影条件は以下となります。
| カメラ | α7CII |
| 焦点距離 | 600 |
| ISO | 400 |
| シャッタースピード | 1/400秒 |
| F値 | 6.3 |
被写体は、木の上にいるヒヨドリです。

木のかなり高い位置に止まっておりましたが、ギリギリ瞳フォーカスで認識できる距離でした。
トリミングにより拡大するとこのような解像度になります。

天候が悪いので、少し画質が荒い気もしますが、600mmで羽毛まで見えることがわかります。
ただ、シャープな写りなのか?と言われると少し疑問に思います。
天候が良くて、ISOを下げることができれば、もう少し良い写りになると感じる。
SEL200600Gは、600mmの焦点距離に価値があるレンズなので、機会損失とシャープさを天秤に掛ける必要があると感じた。
シャープを求めると、600mmF4になるが、価格も大きさも携帯性にデメリットがある。
600mmレンズの入門としてSEL200600Gは良い選択肢であることは間違いないでしょう。
まとめ!SEL200600Gは古いレンズだがまだまだ使える唯一無二の純正望遠レンズ
まとめとして、SEL200600Gは販売から長らく経過しているが、まだまだ現役で使えるレンズだと感じました。
流石にGMズームレンズのような解像度は出ませんが、600mmと価格で納得できる解像度だと思います。
200-600mmとちょうどよいサイズでありながら、サイズや重量もギリギリ手持ちが可能だと評価しています。
また、F値が大きいのでISO感度が上がってしまうことによるノイズが少し気になります。
デメリットは、α7CIIとの相性はやや悪く、グリップの設計上、100%満足できるようなものではありませんでした。
これはレンズ側のデメリットではなく、相性の問題であるため、家電量販店などで試着したほうが良いです。
最後に今回ご紹介した製品のリンクを以下に載せておりますので、興味があればご覧いただければと思います。


コメント